毎日のお風呂や、食器を洗うなど生活に欠かせないお湯を使うためには、給湯器が必要です。
一般的な給湯器の場合、稼働するには電気とガスの両方が必要ですが、給湯器のスイッチは基本的につけたままの人もいれば、必ず使用後はスイッチを切るというという人も多いでしょう。
給湯器のスイッチはつけたままで問題ないのか、また、節約のためには、使わないときには電源を切る方がいいのか気になりますよね。
そこで今回は、給湯器をつけっぱなしにする場合と、使わないときには切り、使うたびにつける場合にかかる光熱費に違いがどれくらいあるのかについて調べてみました。
給湯器をつけておくと、ガス代はかかる?
現在の給湯器は、内部に水が流れてガスが燃焼することで、点火するしくみになっています。
そのため、給湯器の電源がつけっぱなしになっていたとしても、基本的にはお湯を使用しない限り、ガス代はかからないと考えられます。
ただし給湯器をつけておくと待機電力がかかります。
一般的に、コンセントにつながった状態の家電製品や電子機器は、いつでもすぐに使えるように、またデジタルの表示機能やタイマー、リモコンの受信などのため、電力を少しずつ消費しています。
製品を使うときの消費電力よりは小さな電力であっても、年間では多少なりとも電気代に影響する金額となるといえるでしょう。
一般財団法人関東電気保安協会「家庭の省エネ情報 待機時消費電力とは」によると、家庭の電子機器による消費電力量の5.1%を待機電力が占めているようです。
そのうち、ガス温水器(給湯器)の待機電力は待機電力全体の19%で、テレビやエアコンなどをおさえて家庭にある電子機器の中で、もっとも大きいことが分かります。
現在普及している給湯器のほとんどは安全装置がついているようで、もしガス漏れなどの問題が起きた場合でも自動的に止まる仕組みになっており、つけっぱなしであっても安全性に問題はないといえるでしょう。
ただし、10年以上使用している給湯器は注意が必要です。
給湯器には、一般的な使い方をして安全に使用できる期間として「設計標準使用期間」がメーカーによって設定されており、その期間は10年が目安です。
そのため、10年を超えて使用している場合はトラブルが発生しやすくなり、故障する可能性が高くなるため、つけっぱなしには注意する必要があるといえるでしょう。
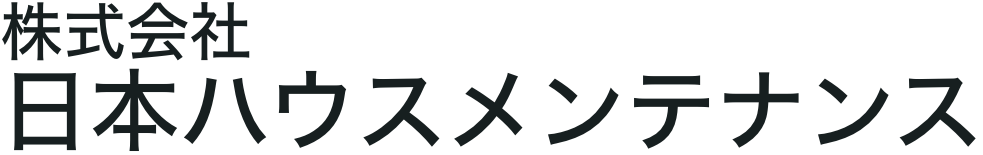
 お問い合わせ
お問い合わせ